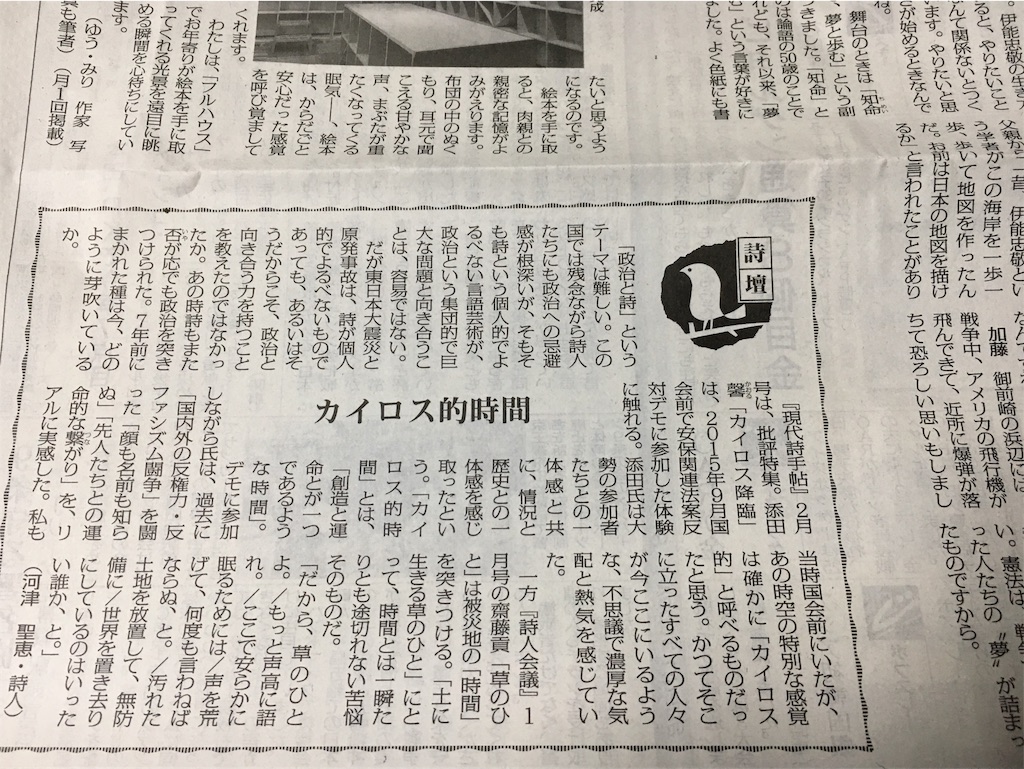バリの中心からRER(高速鉄道)と路面電車を乗り継ぎ、サン・ドニ聖堂まで行きました(方向音痴な私一人では辿り着けなかったであろう)。ボール・エリュアールの生まれ育った街です。
レジスタンスの時代に書かれ、自由を奪われたパリの街に英空軍機から撒かれたエリュアールの詩「自由(リベルテ)」は、この文章の末尾に全文がありますが、本当に素晴らしい詩です。70年以上の時を超えて再び自由の危機が訪れた同時多発テロ後、この詩は建物の壁面に映し出されたりして、パリそしてフランスの人々を再び勇気付けたと聞いています。
サン・ドニはパリ市内とはまた違う雰囲気の移民の多く住む地区です。「不良っぽい街だぞ? 俺も何十年ぶりかで行くけどね」と案内人の元青年の言葉から期待したとおり、駅を降りたった時から美味しそうな焼肉の煙が方々で立ち上る、市内とは全く違う移民の暮らしの匂いのする街でした。
行き交うのは、ほぼアフリカからの移民ばかり。後はアラブ系の人々。もう何世になる人々なのでしょうか。 ふとここは日本で言えば鶴橋のような街に当たるのかなと思いました。そんな空気にむしろ気持をほぐされつつ、路面電車に乗り継ぎ、サン・ドニ大聖堂駅で降りて歩き、ゴチックの威容をほこる大聖堂へ。
大聖堂には歴代王と王妃の棺の数々がありました。遺体はフランス革命の時に労働者たちの手で捨てられ中はもぬけの殻ということらしいです。その代わりにかれらは棺の上の彫刻像となって眠っています。足の方に回り込むと裸足を見せていたり、鎖帷子のような靴下を履いていたり、尖った靴を履いていたり…彫られたのは王政恐らくそこにあるのは、捨てられた 死者たちへの愛惜だけがあるのではないでしょう。のけぞって苦しんだ姿もあり、一人一人の人間として見た庶民の権力者への解釈のようなものを感じさせました。遺骸さえも憎悪によって粉々にされたルイ16世もマリーアントワネットもいました。
教会の近くのエリュアールの部屋のあるサン・ドニ歴史資料館は、なんとお休み。それは残念でしたが、疲れて立ち寄ったカフェでも帰り道をマスターと客が一緒になって考えてくれたり、所々で道をたずねると誰もが親切に応じてくれました。résistanceという路面電車の駅もあってハッとしました。
もちろん犯罪率は決して低くはないはず。しかしどこかエリュアールの詩「自由」の源泉となった空気が、今もたしかに残っているのでしょう。またいつか訪れてみたい街です。
自由
ボール・エリュアール
大島博光訳
小学生の ノートのうえに
机のうえに 樹の幹に
砂のうえ 雪のうえに
わたしは書く きみの名を
読んだ すべてのページのうえに
すべての 白いページのうえに
石や血や 紙や灰のうえに
わたしは書く きみの名を
ジャングルや 砂漠のうえに
小鳥の巣や エニシダのうえに
子どもの頃の こだまのうえに
わたしは書く きみの名を
夜の 不思議さのうえに
日日の 白いパンのうえに
婚約した 季節のうえに
わたしは書く きみの名を
生き生きとした 小道のうえ
遠く伸びた 大道のうえに
ひとの溢れた 広場のうえに
わたしは書く きみの名を
灯(ひ)のともったランプのうえ
また消えた ランプのうえに
わが家の 一家団欒のうえに
わたしは書く きみの名を
許しあった 肉体のうえに
友だちの 額のうえに
差しだされた 手のうえに
わたしは書く きみの名を
思いがけぬ喜びの 窓硝子のうえ
待ちうける くちびるのうえに
沈黙の そのうえにさえ
わたしは書く きみの名を
欲望もない 放心のうえに
まる裸の 孤独のうえに
そして 死の行進のうえに
わたしは書く きみの名を
力強い ひとつの言葉にはげまされて
わたしは ふたたび人生を始める
わたしは生まれてきた きみを知るために
きみの名を呼ぶために
白由よ