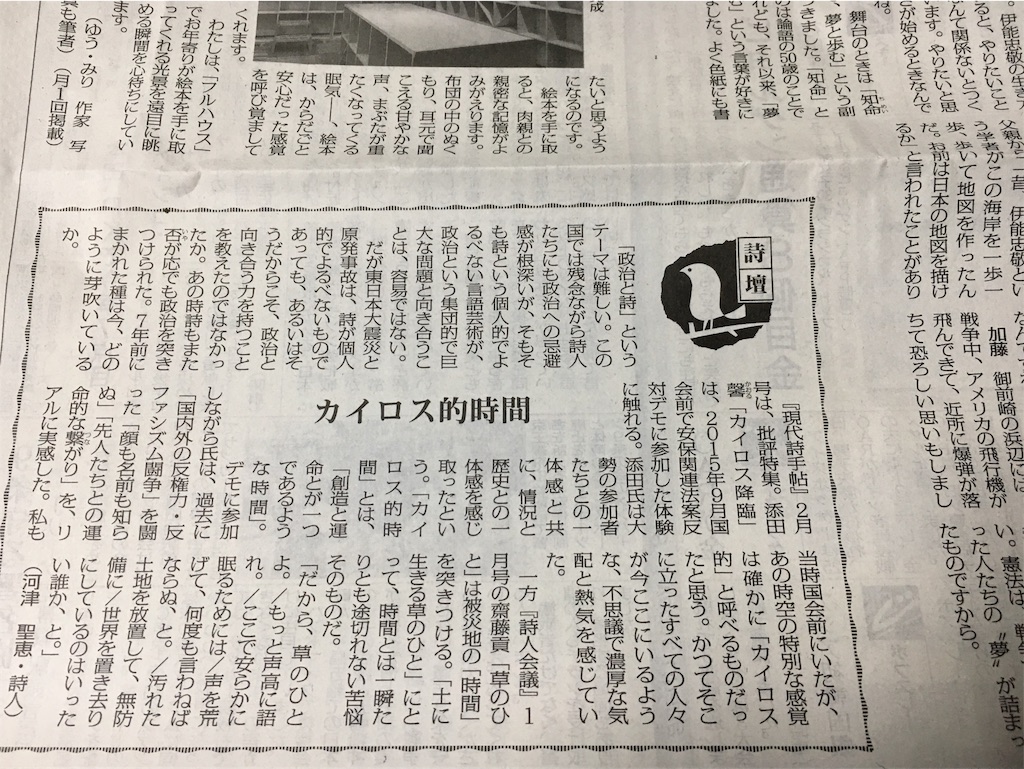キリスト教の信仰を持つある書き手の方の新詩集の帯文を書かせていただいた。来月には刊行されるだろうか。
頼まれた当初は、うれしく思いつつも、一方で不安でもあった。キリスト教の信仰を頭でしかわからない私が、その信仰をもといに書かれた詩に足を踏み入れていいものか、ただ表面を分かったふりで土足で通りすぎることになりはしないかと心が落ち着かなかったのだ。
しかし振り返ってみれば、私も母親が熱心なクリスチャンで、小学生の頃は日曜学校にも通っていた。結局入信はしなかったが、その時の幼心に深い印象を残したのは、「神がいる気配の感覚」だった。例えば、クリスマスに、日曜学校の生徒たちでキリスト降誕劇をやった時(私はマリアの役をやらされそうになって慌てて自分から手を挙げ、一人笛でほそぼそと音楽を奏でる役だった)、暗幕で光を遮り、厩の闇の雰囲気を出したのだが、その時の闇の濃さは確かに遥かな時間を超え、まさに劫初の闇のものとして不思議に実感された。また教会の庭にうららかな日が差した春には、輝く噴水や花々を見つめながらシスターが、「すべてに神様の愛が宿っているんですよ」と言った時、本当に細部まで眩しく照り返された気がしたこと。その後、思春期が始まったせいか、内面にまで介入されたくないという気持がつよまり、教会から足は遠のいてしまった。しかしあの時期に、果たして信仰の萌芽があったのだろうか、あるいはむしろ不信の萌芽が始まっていたのか。客観的には分からないが、今の自分を省みると恐らく後者ではないかとも思うが、違うかも知れない。
話はそれたが、問題は信仰を持つ書き手の詩を信仰を持たない読み手がどう読んだらいいか、ということである。まず「信仰者の詩」と銘打っていたら、読み手はどう感じるだろう? 恐らく少なからぬ読み手が、「ああ違う世界の人ね」と敬遠するのではないか。もちろん、確かに神の愛への賛美を天真爛漫にうたう詩がないわけではないが、偏見からそう見えてしまう場合が少なくないはずである。それゆえ実際そう銘打たれることは殆どない。しかし信仰とは信仰者にとってはその精神の根底にあるもので、恥ずべきものでも敬遠していいものでもない。その人の詩を深く理解しようとするなら、その人の信仰はむしろ欠かせない要素である。さらには、書き手は信仰を持つにもかかわらず、なぜ詩を書いているのかというところにまで想像が及んでいかなければならないのではないか。
しかし同じ信仰を持たない者にとっては、実際それは至難の業である。
だから今回帯文を書くに当たって、信仰にたいする自分の鈍感さを何とか揺さぶっておかなくてはならないと思った。そこでふっと心に浮かんだのが、石原吉郎である。八年間シベリアに抑留され、帰国した直後から詩を書いたが、やがて十五年後に抑留体験と信仰をめぐるエッセイを書き始めた。私も三年前に刊行した『闇より黒い光のうたをー十五人の詩獣たち』で「詩獣」の一人として石原を取り上げたが、その後何かずっと書き足りなかったものがあると感じていた。他にも石原についての論集がいくつか出たが、そのどれもにも同じような不全感を感じざるをえなかった。足りないのは、石原の信仰という観点である。それは信仰をエピソードにしてしまうような批評の文脈には絶対に乗り切らない。石原と同じ信仰を持ち、それゆえ同じ希望そして同じ絶望を知る者だけが、信仰を中心としてそこから内面深くに分け入ることが出来、ようやく十全とした石原論を生み出すのだと思う。
しばらく前に買って少しだけ読んで本棚にあった柴崎聰『石原吉郎 詩文学の核心』(新教出版社)が、目に付いた。石原と同じ信仰者による石原論である。石原のことばにミリ単位で迫る論の運びに、圧倒された。買った当初はそう思わなかった。恐らく今回帯文を書くに当たってキリスト教の信仰を理解したいという、私自身の思いがあるから、この本が石原吉郎に迫っている深度をようやく感じ取れたのだと思う。当初は「信仰者が描いた石原吉郎像はどうかなあ」と思っていたようだ。その時は私自身が石原論を書くために読んだので、自分の中にある抑留体験を核とした石原像を優先したのだろう。しかし今はこの本の、信仰というテーマから見た石原像や詩の解釈が恐らく最も正解に近いだろうと感じる。私の中で書き足りなかったと思っていた部分が、みるみる埋められていくのが分かった。石原吉郎のいわば実存に近づきたいと思うならば、これは最良の手引きである。
この本で引用された石原吉郎のエッセイの次のことばは、信仰者の詩とは何かをおのずと物語っているように思う。
「信仰とは、いわばありえざる姿勢の確かさである。そしてそのような姿勢にリアリティを与えるものが、不安としてのことばであるように、私には思える。信仰というすがたのあやうさと、ことばのあやうさが、そこで生きいきと対応する。その対応への不安が、信仰のリアリティであり、それをうらがえせば、存在の根源的な不安さのリアリティとしてのことばではないかと私は思う。」(「信仰とことば」)
信仰者の詩は、詩というものの本質が不安にあること、そして今むしろそうあるべきことを、教えてくれる「不安に目覚めた詩」なのかも知れない。