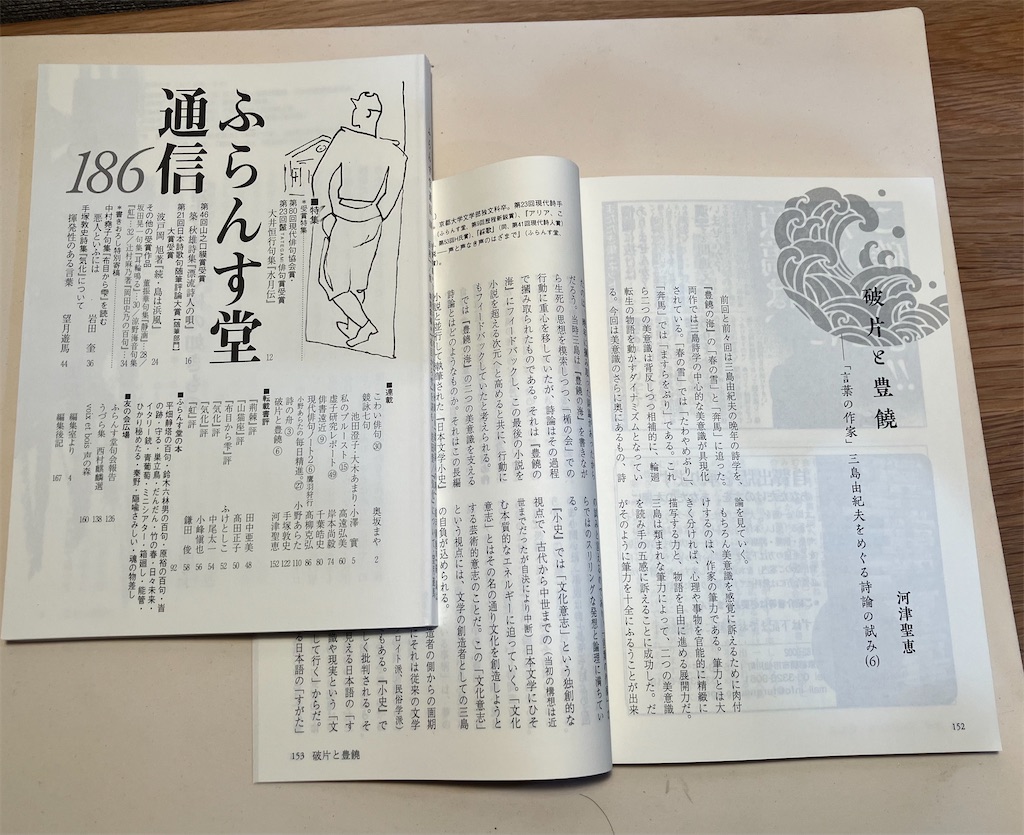『ふらんす堂通信』186に、「破片と豊饒ー『言葉の作家』三島由紀夫をめぐる詩論の試み(6)」が掲載されました。
今回から『豊饒の海』とほぼ同時期に書かれた『日本文学小史』を分け入っていきます。今回はその序章に当たります。
『小史』は、各古典において、「文化意志」(文化を創造しようとする芸術的意志)を探るという、三島ならではの特異な文学史です。三島は文学者としての最後の営為として、『豊饒の海』という、戦後という空虚を言葉の海の煌めきでつかのま満たす、長大な物語を書きました。そしてこの物語を書きながら、一方で『小史』にも挑みつつ、倭建命をはじめとして、紀貫之や藤原定家といった詩人たちと同様、みずからも文化意志に突き動かされていることを自覚していったのだと思います。『小史』はその自覚の上に立って、「芸術作品を書くように」書かれた文学史です。またそこで発見された詩論が、『豊饒の海』の展開に反映されてもいます。例えば「奔馬」で自分が撃った鳥の死骸を抱きながら嘆く飯沼勲と、詩性と暴力性を担わされて野に追放された倭建命は、明らかに重なり合う存在です。そのように『小史』は『豊饒の海』と映りあっています。『小史』をつらぬく詩論をしっかり読み解くことが、三島由紀夫の自決に至るまでの内面の葛藤を考える上で、非常に重要だと思います。その結果、三島由紀夫の詩性、さらには詩というものそのものにも、これまでになかった角度で光を当てられるのではないでしょうか。
ちなみに今回、私自身の詩集『夏の終わり』の詩篇が、『豊饒の海』の「回想の像」が密かにオーバーラップしていることにも触れました。
『ふらんす堂通信』は「ふらんす堂」のオンラインショップから購入出来ます。ぜひご高覧下さい。